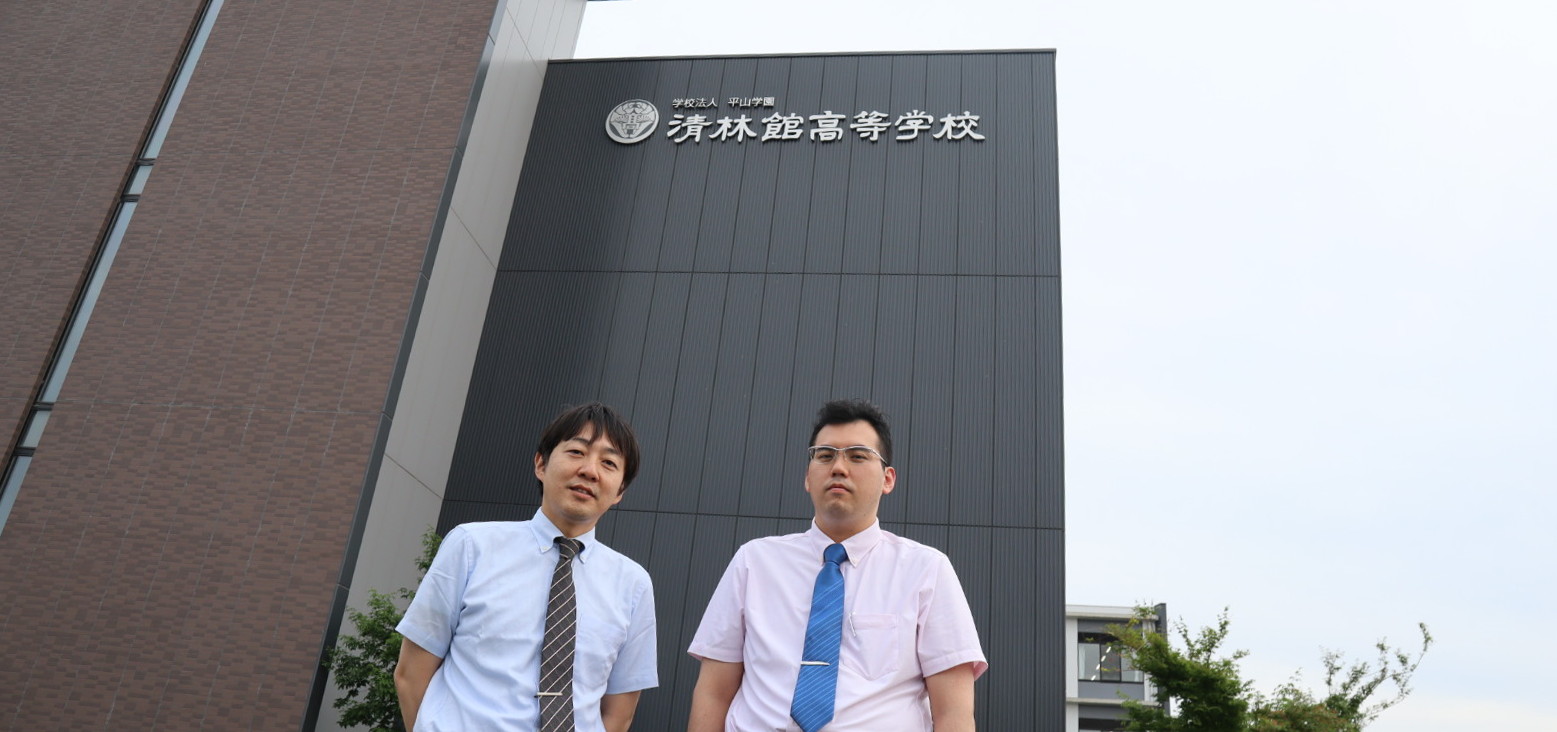導入事例:学校法人平山学園 清林館高等学校
2022年度からノウンの英語教材をご採用いただいている学校法人平山学園 清林館高等学校の村瀨一雄英語科主任、大嶋良輔教諭にお話を伺いました。
(写真左:村瀨一雄先生 写真右:大嶋良輔先生)
― 清林館高等学校について教えてください。
本校は大正15年創立の今年創立98周年になる学校で、もともとは女子高等学校だったのですが2001年に現在の「清林館高等学校」へ校名を変更するとともに男女共学化しました。
本校では「21世紀型教育」の取り組みの一環としてICTの活用を重視し、生徒全員一人一台iPadを活用した授業を展開しています。
― ノウンのデジタル教材を英語の授業に導入した経緯を教えて下さい。
共通テスト対策としてiPadを活用できる英語のリスニング教材を探していたのですが、なかなか良いリスニング教材がありませんでした。
CDによるリスニング音声がついている教材もありましたが、そもそも最近はCDを聞くことができる環境を持っていない家庭が増えてきています。
そんなときに取引先であった教育図書専門取次の株式会社日教販に相談したところ、
Z会ソリューションズ(以下、Z会)から書籍の英語リスニング教材の「共通テストドリル 英語リスニング 10minutes(以下、共通テストドリル)」をノウンのデジタル教材にするのにご協力いただけることになり、
書籍と一緒にその「共通テストドリル」のノウンのデジタル教材も購入することになりました。
さらにリーディング能力向上のために同じくZ会の「Reading Express Book」シリーズもノウンのデジタル教材にしていただき、その書籍とノウンのデジタル教材を1年生、2年生に導入しています。

― ノウンのデジタル教材はどのようにご活用されていますでしょうか。
主に英語の補習のリスニング学習にノウンを活用しています。
ノウンではドリルの学習結果が最後に採点結果として表示されますので、生徒がドリルで学習した後、教員がその採点結果画面を見て指導に利用しています。
採点結果には問題を解くのにかかった時間も見ることができる点も便利で活用しており、ノウンの採点結果に基づいて生徒への指導が非常に有効にできていると感じています。
― ノウンを導入して効果はありましたか。
iPadを使って学習する習慣がつきました。生徒たちがリスニングの音声を頑張って聞き取っている姿や、次はどのような問題かわくわく感を持ちながら学習している様子が見られるようになりました。
また、ネイティブの英語を聞くチャンスがこれまでは英語のネイティブスピーカーの先生の授業だけでしたが、それにプラスしてノウンのデジタル教材でリスニング学習が自分で週一回とか週二回できるようになりました。
共通テストを目指す生徒に対しては「これ聞いたことがある」「あのときやった内容だ」と聞き馴染みを持ってもらうことが狙いで、
3年生ではリスニングがある程度すんなりできるようになり、ポイントもつかめるようになってきているのを肌で感じています。
― ノウンの導入はスムーズにできましたか。
最初はノウンのデジタル教材のダウンロードとログインが必要なので、クラスで一斉に行うとネットワークが混雑して時間がかかるということがありましたが、2回目以降はスムーズに利用することができました。
ノウンのデジタル教材は音声データも含めて最初にiPadにダウンロードするので、学習時に音声を再生するときもネットワークの混雑度合いに影響を受けないという利点があります。
Webタイプの教材だと音声データは生徒一人ひとりが学習のたびに毎回ダウンロードすることになるので、ネットワークが混雑している場合にリスニングの音声が途切れてしまうことがあり、
せっかくリスニングを真面目にやっているのに途中で音声が途切れてしまうと集中も切れてしまうという問題があります。
共通テストのリスニングは30分1本勝負で、そのリスニングに対応できる集中力も必要なので、その点ノウンのような教材をダウンロードするタイプのほうが良いですね。

― ノウンのデジタルドリルは書籍と一緒に購入することもできるようにしていますがこの点はいかがでしょうか。
これまではアプリを導入しようとすると、これまで取り引きのなかった企業から新たに購入する必要があったり、購入に使える予算がなかったりと購入しにくかったのですが、
ノウンのデジタルドリルは通常の書籍と同じように学校に教科書や教材を納入している書店から副読本などを購入する教材費として購入できるので非常に購入しやすかったです。
副読本を購入したら特典としてアプリがついてきたという感じでした。
― 今後のデジタル教材へのご要望はありますか。
他の出版社の教材も、ノウンのような共通プラットフォームのデジタル教材として提供してもらえると、
利用する私たち教員や生徒としても一つの共通プラットフォームに慣れるだけで良いので、そうなれば非常に理想的な学習環境になると思います。
― 本日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございました。